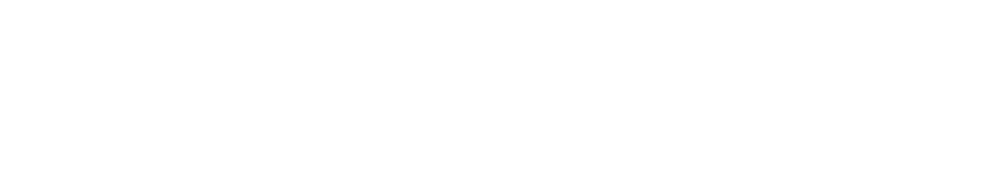室戸には、なんだか頼もしい若者が多い。
約2年前に訪れたときもそう感じたんですが、今回もまたそんな印象を強くしました。
友人に連れていってもらった備長炭の炭窯。
「室戸で暮らしたいけど仕事がない」という若者たちの仕事をつくりたい。
そんな思いで、この炭窯はつくった若者がいました。

室戸は「ウバメガシ」という木が群生している場所が数多くあり、昔から備長炭の生産が盛んな場所だったそうです。
彼が備長炭の窯を立ち上げようと思ったきっかけは、新聞の記事でした。
国内シェア8割だった中国産の備長炭が、森林保護を理由に輸出を制限されることになったという記事を見たからなんだそう。
「これだ!」と思って、すぐに室戸の炭窯に弟子入りを志願。
2年間の厳しい修行を経て「炭玄」を立ち上げました。
ここにある炭窯も小屋も全て、自分でつくったそうです。

行動するって、すごく大変なこと。
そしてそれを続けるというのは、さらに大変なこと。
でも彼が「炭玄」を立ち上げてからもう10年が経過し、数人の若者が彼のもとで炭焼きを覚え独立していきました。
着実に、仕事が、雇用が、室戸で生まれています。
そして2014年、51年ぶりに備長炭の生産量が和歌山を上回って、高知が1位となりました。
それでもまだ、備長炭の生産が需要に追いついていないと言います。
すごいことですよね。

とはいえ、炭焼きは重労働です。
山に入って木を伐採するところから始まり、炭焼きが始まったら炭を窯から出すまで昼夜問わずにつきっきりとなります。
従来のやり方のままでは、若者はついてこない。
そこで、ここでは働き方も工夫しています。
シフト制にしたり、きちんと休める体制をつくっているのです。
第1次産業の現場では「後継者がいない」と言いながら、働き方自体を見直すことって少ないような気がします。
これ、結構大事だと思うんです。
「従来の働き方では嫌だ!」という意見は、「やる気がない」と変換されてしまう。
でも、「従来のやり方以外方法はない!」って意見も、「考える気がない」=「やる気がない」と言えると思うんですよね。
「これが正しい」や「これが当然」も、1度は疑ってみる必要があるのではないでしょうか。

備長炭は同じ窯で焼かれたものであっても、炭のグレードによって分けられます。
炭玄さんでは、1番グレードの高い炭に通常よりも厳しい基準を設け、他と同じグレードのものを買っても、他より品質がよいものであることを心がけているそう。
ものづくりへのプライドですね。
私も詳しく説明できるほど炭焼きについて知っているわけではありませんが、炭窯の排煙口は小枝を使ってこんな微妙な調節をされていました。

「田舎の資源を使って起業」みたいな話がよくありますが、それは、炭玄さんのように地に足をつけながら着実に積み重ねていくものであってほしい。
そして技術の継承と働き方は分けて考えることは、これからもっと必要になってくると感じました。
四方山商店をフォローして更新情報をチェックしよう!
▼ Facebookでフォロー(いいね!クリック)▼ Twitterでフォロー
Follow @yomoyama_shop